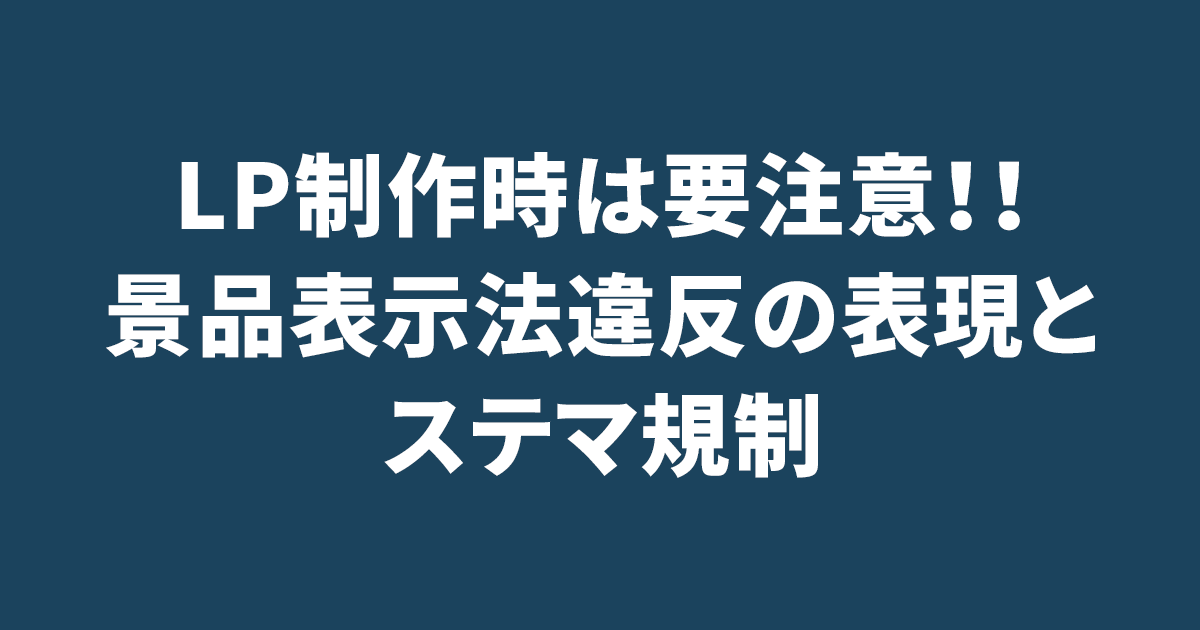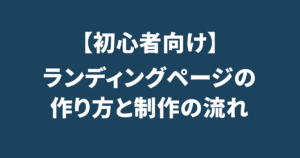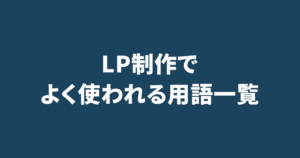ランディングページを制作する際や広告運用する際には、薬機法や景品表示法といった法律に抵触しないように気をつけなければなりません。
その中でも、この記事では「ランディングページ制作時に注意するべき景品表示法の規定と違反になる表現」について解説します。
この記事を読むと、
- 景品表示法とは何か
- 景品表示法で禁止される内容
- 景品表示法違反になりうる表現例
についてわかります。
また、2023年10月1日にはステマ(ステルスマーケティング)に関する規定が追加されるなど、近年注目を浴びることも多い法律です。
景品表示法について知りたい方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。
▼ランディングページの作り方や制作の流れについては、こちらの記事もあわせてご覧ください。
▼記事を読んでいてわからない用語があれば、下記記事も参考にしてみてください。
景品表示法は不当表示や過大な景品の提供を規制する法律
景品表示法は、正式には「不当景品類及び不当表示防止法」といいます。
事業者による不当な広告や表示、過大な景品の提供などを規制することより、一般消費者が自主的かつ合理的に商品やサービスを選べる環境を確保することを目的としています。
景品表示法では、大きく下記2つの項目が規制されています。
- 不当な表示の禁止
- 過大な景品類の提供の制限および禁止
「景品表示法」について、詳しくは消費者庁のHPをご参照ください。
不当な表示の禁止
「不当な表示の禁止」は、さらに大きく3つに分類されます。
優良誤認表示の禁止
「優良誤認表示」とは、商品・サービスの内容についての表示のうち、
- 実際のものよりも著しく優良であると、消費者に誤認させる表示
- 事実に相違して競合事業者のものよりも著しく優良であると、消費者に誤認させる表示
が該当します。
商品・サービスの内容には、「品質・規格」のほか、それらに間接的に影響を及ぼすもの(原産地、製造方法、考案者、受賞歴、有効期限、他社・お客様からの評価など)も含まれます。
優良誤認表示に該当しうる例
- 「お客様満足度95%」と表示していたが、実際にはお客様満足度が60%だった
- 「〇〇牛(ブランド牛)」と表示していたが、実際には〇〇牛とは認められない牛肉だった
- 「◯◯大学合格実績No.1」と表示していたが、実際にはNo.1ではなかった など
有利誤認表示の禁止
「有利誤認表示」とは、商品・サービスの取引条件についての表示のうち、
- 実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると、消費者に誤認させる表示
- 競合事業者のものよりも取引の相手方に著しく有利であると、消費者に誤認させる表示
が該当します。
商品・サービスの取引条件には、消費・サービスの「価格」のほか、数量・支払い条件・保証内容なども含まれます。
有利誤認表示に該当しうる例
- 「今だけ50%OFF」と表示していたが、実際にはいつもその価格で販売している(二重価格表示)
- 「安心保証5年」と表示していたが、実際には全額保証されるのは最初の1年間でその後は一部しか保証されない
- 競合他社と比較して「最安値」と表示していたが、実際にはさらに安価で販売している事業者があった など
その他誤認されるおそれのある表示の禁止
「その他誤認されるおそれのある表示」とは、上記「優良誤認表示」「有利誤認表示」に該当するもの以外で、内閣総理大臣が指定した不当表示のことです。
現在指定されているものは、以下の7つです。
- 商品の原産国に関する不当な表示
- 無果汁の清涼飲料水等についての表示
- 消費者信用の融資費用に関する不当な表示
- おとり広告に関する表示
- 不動産のおとり広告に関する表示
- 有料老人ホームに関する不当な表示
- 一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示(ステマ規制)
「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」の項目は、2023年10月1日に追加されたもので、いわゆる「ステマ(ステルスマーケティング)」のことです。
ステマとは、広告であるにもかかわらず広告であることを明示せずに宣伝することを指します。
近年ステマが問題視されることが多くなり、景品表示法で定める禁止項目に追加されることとなりました。
「ステマ規制」について、詳しくは消費者庁HPをご参照ください。
過大な景品類の提供の制限および禁止
景品表示法では、景品(おまけ、特典)を過大に提供することは、消費者の正常な判断を阻害する原因になるとしており、過大な景品類の提供を規制しています。

「景品類」は、主に以下の3つに分類されます。
- 一般懸賞による景品(例:くじによる抽選やクイズ正解者に対する特典として提供される景品)
- 共同懸賞による景品(例:商店街など一定の地域内の事業者が共同で行う抽選会の景品)
- 総付景品(例:購入特典や来店特典として全員に提供される景品)
このうち、ランディングページで問題になりやすいのは、「総付景品」です。
総付景品は商品やサービスの購入者に対してもれなく景品を提供する場合などに該当し、景品類の最高額は、
- 取引価格が1,000円未満の場合は「200円」
- 取引価格が1,000円以上の場合は「取引価格の20%」
と制限されています。
そのため、ランディングページで商品やサービスを販売する際に購入特典を設けることもあると思いますが、1,000円以上の商品やサービスの場合は、特典内容の価格を商品価格の20%以内にとどめる必要があるのです。
購入者に対する特典内容が過剰にならないよう注意しましょう。
景品表示法に違反した場合
景品表示法に違反した場合、「措置命令」または「課徴金納付命令」を受ける可能性があります。
措置命令では、一般消費者に与えた誤認を排除することや、再発防止策を実施することなどが事業者に命じられます。
措置命令に従わない場合は、2年以下の懲役または300万円以下の罰金が課せられます。
課徴金納付命令では、原則として、不当表示の対象となる商品・サービスの売上額の3%相当額の納付を命じられます。
まとめ:正当な表示や景品の提供を行い、信頼を損ねないようにしよう
以上、「ランディングページ制作時に注意するべき景品表示法の規定と違反になる表現」について解説しました。
ランディングページ制作や広告運用においてはさまざまな法律を遵守しなければなりませんが、特に景品表示法は近年問題となるケースも多くあります。
売上を上げることはもちろん重要ですが、それに伴って一般消費者の利益を阻害することがあっては絶対にいけません。
事実や客観的な根拠に基づいた正当な表示や景品の提供を行い、事業者としての信頼を損ねないよう注意しましょう。